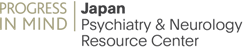遠隔診療として行われる短期認知行動療法は自殺企図の減少に有効
提供元:AJ Advisers LLCヘルスデージャパン
ビデオ通話による遠隔診療で提供される短期認知行動療法(brief cognitive behavioral therapy;BCBT)は、過去1週間に自殺念慮を抱くか、過去1カ月間に自殺を企図したかの一方または両方が当てはまる成人において、自殺企図の減少に有効であるという研究結果が、「JAMA Network Open」に2024年11月12日掲載された1。
米オハイオ州立大学のJustin C. Bakerらは、自殺リスクの高い成人に対するビデオ通話によるBCBTが、自殺企図および自殺念慮の減少に有効であるかを検討した。対象は、Scale for Suicide Ideation(SSI)スコアが5点以上、または、Self-Injurious Thoughts and Behaviors Interview-Revised〔SITBI-R〕の項目を用いた評価で過去1カ月以内に自殺未遂の経験があると判定された18歳以上の者で、BCBTを受ける群と現在中心療法(present-centered therapy;PCT)を受ける群にランダムに割り付けられた。BCBTは感情を制御する方法や、嫌な感情を良い感情に変えることなどを教える、一定時間内に終了する心理療法で、3つのフェーズ(計12セッション)で構成されている。一方、PCTは、目下の生活でストレスになっていることや、精神症状に直接・間接的に関係する厄介なことに対する反応を、適応的・順応的なものにしていくことを目的とした、一定時間内に終了する心理療法である。主要評価項目は、SITBI-Rで評価した自殺企図(中断や阻止されたもの、実行に至ったもの)、副次評価項目は、対象者がSSIを用いて評価した自殺念慮の強度とした。解析はITT解析とした。1年間の追跡期間中に1回以上、自殺企図した者の割合の比較には、カプランマイヤー法とCox回帰モデルを使用した。自殺企図の回数の比較には、ポアソン回帰モデルとAnderson-Gillモデルを使用した。自殺念慮の強度の比較には一般化線形混合効果回帰モデルを適用し、そのモデルにおいては、SSIスコアは連続変数、治療の種類や時間などは固定効果、切片と傾きはランダム効果とした。
最終的に、96人(BCBT群51人、PCT群45人、平均年齢〔標準偏差〕31.8〔12.6〕歳、女性66.7%)が解析対象となった。ベースラインから12カ月後までの間の自殺企図回数は、PCT群では12人(推定割合35.6%)での56回であったのに対し、BCBT群では11人(推定割合30.0%)での36回であった。自殺を企図した者の割合には有意差が認められなかった(ログランク検定によるχ²=0.4、P=0.50、ハザード比〔HR〕0.91、95%信頼区間〔CI〕0.37-2.27、P=0.84)。しかし、自殺企図の1人当たりの回数は、ポアソンモデルによる解析では、BCBT群で0.70回(範囲0.00〜8.00回、95%CI 0.49-1.00)、PCT群で1.40回(範囲0.00〜10.00回、同1.07-1.84)で、前者が有意に少なかった(Wald検定でのχ²=9.3、P=0.002)。自殺企図リスクは、Anderson-Gillモデルによる解析で、BCBT群がPCT群よりおよそ41%有意に低かった(HR 0.59、95%CI 0.36-0.96、P=0.03)。自殺念慮の強度は、両群とも有意に減少した(F4,330 = 50.1、P< 0.001)。ただし、傾きには両群間に有意差はなかった(F4,330 = 0.2、P =0 .91)。
著者らは、「われわれの知る限り、本研究は自殺リスクの高い者を遠隔診療で安全かつ有効に治療できることを示した最初の研究である。今回の結果は、確立されたエビデンスに基づく治療法から逸脱することなく、治療対象を広げられることを意味している」と述べている。(HealthDay News 2024年11月15日)
Copyright © 2024 HealthDay. All rights reserved.
Photo Credit: Adobe Stock