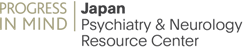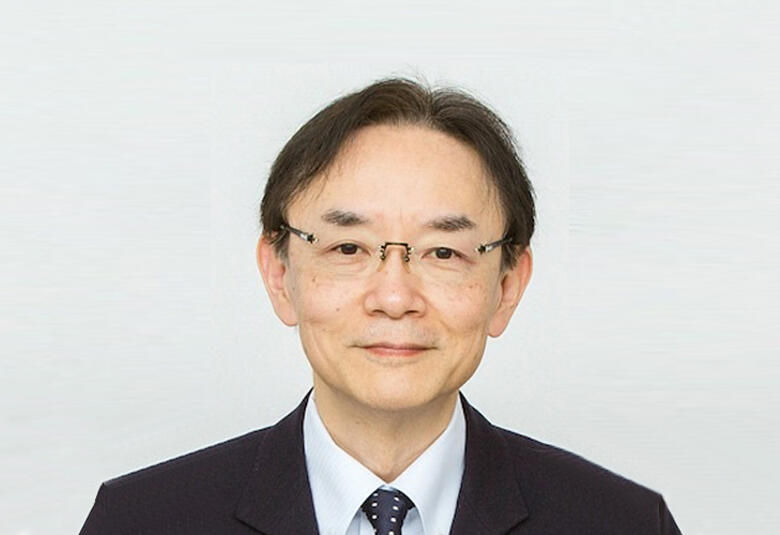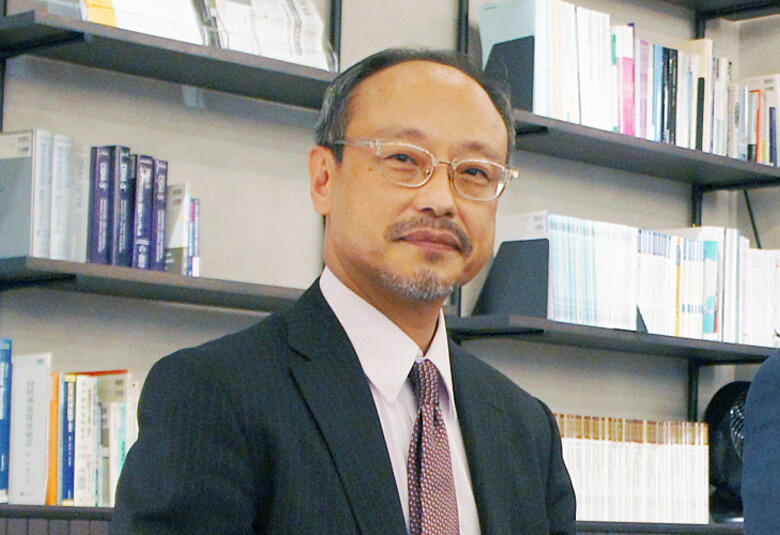感染症と文明の歴史からみたCOVID-19と現代社会の関わり~COVID-19感染拡大を精神科医の視点で考える Vol.7
木下 利彦先生(関西医科大学精神神経科 教授)
2021年6月開催予定の第117回日本精神神経学会学術総会で大会長を務められる木下利彦先生に、コロナ禍において目指す学会のあり方についての考えとともに、日常臨床を通じて感じられたコロナ禍の影響などについてお話を伺いました。
―2021年の第117回日本精神神経学会学術総会は、どのような会になるでしょうか。
2021年6月の開催予定時期の時点で、COVID-19の影響がどの程度残っているかを見通すことは困難ですが、その影響は小さくはないと思います。欧米ではさらなる感染拡大がみられ、いまだ収束の時期も目処が立っていません。来る学術総会では、現在進行形で拡大するCOIVD-19についても、有益な情報を共有できるようにしたいと思っています。
COIVD-19関連以外では、(1)精神科診療の最新トピックス、その対極としての(2)精神医学の古典的知見、さらに(3)精神医学と芸術との関連、といった3テーマを柱として掲げる予定です。これまでの会とは一味異なる、知的刺激にあふれた会にしたいと考えていますので、ご参加予定の皆様にはぜひとも楽しみにしていただけたらと思います。
また、オンサイトでの発表とともに、アーカイブの発表データを後でオンデマンド視聴できるようにしたいと考えています。別会場で興味深いセッションが同時進行で発表されていて一方しか聴講できず、残念な思いをした経験のある方は多いと思います。オンデマンドであれば、このような問題も解決しますし、都合の良いタイミングで繰り返し視聴できるメリットもあります。加えて、従来、海外在住の先生を招聘して講演を依頼すると、渡航日程の調整や、交通費・宿泊費などの労力・費用がかかりましたが、オンラインで講演いただく場合は、これらの負担が大きく軽減されます。IT活用で得られる恩恵を大いに享受し、より多くの方に参加いただける会にしたいと思います。
―来る学術総会では、感染症と文明の歴史を切り口に精神医学を俯瞰する、コロナ禍において時宜を得たセッションも予定されていると伺っています。感染症と文明、精神医学は歴史的にどのように関わりあってきたのでしょうか。
有史以来、我々人類は感染症の大流行により社会が変化したり社会の変化により感染症が流行したりというように、感染症と人類社会が相互に影響を及ぼしあう経験を幾度となく重ねてきました。現在のコロナ禍での状況も、歴史を振り返ってみると近似する出来事がいくつかあるように思います。
14世紀のヨーロッパで発生したペストの大流行は、同地域の人口の約3分の1が死亡するほどの大惨事であったと言われています。その後、ヨーロッパのカトリック教会を中心とした社会構造に変化が生じ、ルネサンスの文化が花開いたとされています。ペストを経たルネサンス期の絵画には、以前とは異なり人間の感情を表出している作品が多くみられるようになりました。
15世紀後半になると、フランスの侵攻を受けていたイタリアのナポリで梅毒が流行しました。また、コロンブスのアメリカ大陸上陸以降、南北アメリカ大陸で天然痘の大流行が起き、アメリカ先住民人口の激減を招きました。これらは、人の移動という社会の変化によって感染症の流行が起きた代表的な例です。
このように、感染症は常に人類の身近に存在していたものであり、感染症の流行により何かがリセットされては新しいものが生まれるという、そうした歴史が繰り返されてきたようにも感じられます。
現在進行形で蔓延するCOVID-19は、人が航空機などで容易に国境を超えて移動できるようになった現代社会の利便性こそが、短期間で世界的な大流行をもたらした主たる原因だと考えています。ただ、COVID-19を経た社会が、中世のヨーロッパのように大きな変貌を遂げることになるのかどうか、予測することは容易ではありません。アメリカ合衆国の政治学者であるサミュエル・P・ハンティントン氏が1996年に著した『文明の衝突(原題:The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order)』を読むと、約四半世紀前の時点で、まさに最近のニュースで取り上げられている国際情勢を的確に予測した記述が散見され、驚かされます。本書の内容が全て正しいというわけではありませんが、アフターコロナの社会の形を予測する上で、重要な示唆を与えてくれている書籍と思います。興味がある方は、是非ご一読いただければと思います。
感染症と精神医学の関連性についても、これまで数々の議論がありました。15世紀に流行した梅毒に対する効果的な治療法は、20世紀にペニシリンが開発されるまでの長い期間にわたり存在していませんでした。その間、梅毒の中枢神経系への感染である神経梅毒により神経症状を呈した患者さんが一定の頻度で存在していたことは想像に難くありません。最近では東京慈恵会医科大学の近藤一博先生が、ヒトに寄生する微生物を含む遺伝子群(メタゲノム)に着目した研究により、ヒトヘルペスウイルス6B(HHV-6B)の遺伝子SITH-1とうつ病発症との関連性が示唆されたと報告1するなど、ウイルス学と精神医学を融合した研究も行われています。アルツハイマー型認知症においても、その原因の1つに炎症があるという考え方から、抗生物質ミノサイクリンの抗炎症効果について検討した研究2も行われています。感染症と精神医学の関連性については未だ議論の余地があるものの、興味深い研究分野だと思います。
―コロナ禍により、先行きの見えない不安が社会に蔓延しています。先生の日常臨床で、このコロナ禍に特徴的と思われる患者像があれば教えていただけますか。
まず、躁状態を呈する患者さんが増えたという印象があります。双極性障害の気質がある方だと思いますが、気分が高揚して多弁になったり、多額の金銭を浪費したりして、見かねた家族が連れてくるといったケースが何件かありました。うつ病と診断された患者さんでも、全員ではないものの躁転したケースもありました。従来、うつ病で病態水準の悪いケースは特に躁転するリスクがあるといわれてきました3が、まさに現在、コロナ禍での極度のストレスまたは長期にわたるストレスが、うつ病の躁転を招くきっかけになっているのではないかと推測しています。コロナ禍が直接的にストレスをもたらすだけでなく、コロナ禍に伴う生活環境の変化や家庭内での問題なども大きなストレスの要因となっていることと思います。また、以前のストレス発散方法が自粛生活などでできなくなっている人も多いことと推察します。
そのほかに気づいたこととして、3ヵ月処方を行っている維持期の患者さんで、前回受診からの3ヵ月間について、入院や大きな怪我、家族の死といった何かしらの大きな出来事が身の上に起きたと話す患者さんが増えた印象を持っています。以前であれば「特に変わりありません」という話から、普段どおりの薬の処方をして診察を終える患者さんが大半であったにもかかわらずです。こうした患者さんの言動の変化とCOVID-19との関連性は不明ですが、コロナ禍で何かしらのストレスをより多く抱えるようになったことを反映しているのではないかと推測しています。
―関西医科大学総合医療センターは、新型コロナウイルス感染者の受け入れ病院と伺っています。精神科の日々の診療業務にはどのような影響が生じているかについて、教えてください。
当施設は、敷地の中央にホスピタルガーデンというサッカーコート1面をつくれるほどの広い空間があり、それを囲むように東側に本館、北側に精神科のある北館、そして南側に新型コロナウイルス感染者を受け入れている救命救急センターがある南館があります。南館がホスピタルガーデンをはさんで対極に位置していたこともあって、精神科の入院患者さんも我々スタッフも、新型コロナウイルス感染者の受け入れについてさほど心配することはありませんでした。他の精神科病院でクラスターが発生し、搬送されてきた患者さんを当施設の救命救急センターが受け入れ、回復後に当施設の精神科で治療を開始した患者さんはいましたが、このようなケースでも特に心配したことはありません。
救命救急センターの職員は皆、新型コロナウイルス感染者のケアに本当に尽力されています。家族への感染を予防するために、ホテルへ宿泊するなど自主的に隔離していた医師や看護師も多くいました。当科は、そのような救命救急センターの職員の精神的なケアにあたりました。今後も、刻々と変わる状況の中で、その時々に応じたケアを行っていきたいと考えています。
取材/撮影:ルンドベック・ジャパン Progress in Mind Japan RC
取材日:2020年10月22日
取材場所:ルンドベック・ジャパン株式会社
Progress in Mind Japan Resource Centerは、会員の皆様が安心して自由に意見交換できる場を提供することを目指しています。
本コンテンツに登場する先生方には、Progress in Mind Japan Resource CenterのWebコンテンツ用の取材であることを事前にご承諾いただいたうえで、弊社が事前に用意したテーマに沿ってご意見・ご見解を自由にお話しいただき、可能な限りそのまま掲載しています。
お話の内容は、すべての患者様や医療従事者に当てはまるものではなく、またそれらの内容は弊社の公式見解として保証するものではありません。