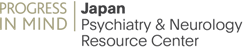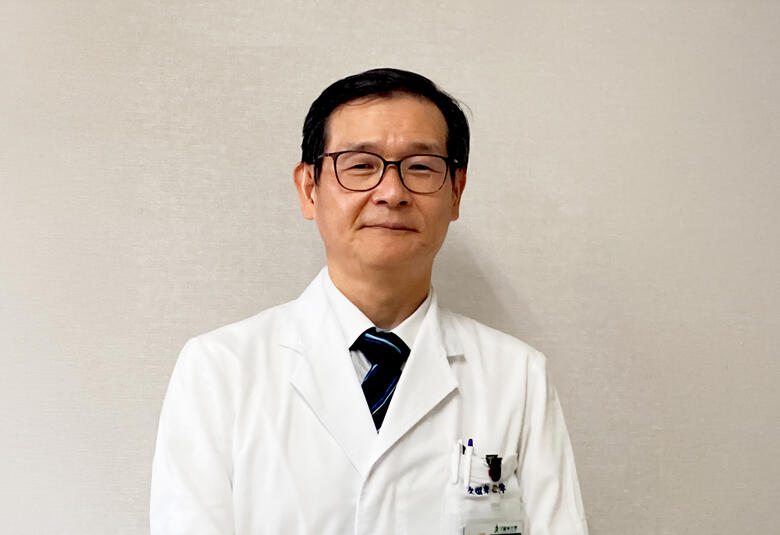「次世代を担う精神科医が考える 医療の質向上に向けた実践とキャリア像」(前編) 「臨床・教育・研究のリンク」を磨き上げ、次の世代にバトンを渡す 精神医学クローズアップVol.20
精神医学や精神科医療は時代とともに大きく変化しており、臨床・教育・研究を取り巻く環境も以前とは異なってきています。そのような中で、次世代を担う精神科医のスキルアップ、精神科医同士のネットワークづくり、キャリア構築はより重要になっています。
また、スキルアップやキャリア構築に前向きな若手の精神科医にとって、同世代の臨床の実践活動やキャリア像に興味があるのではないでしょうか。
本座談会では、臨床・教育・研究において多くの役割を担い、次世代をけん引する3名の先生方にご参集いただき、これまでの歩みや現在注力していること、自身のキャリアや将来像について議論いただきました。
前編では精神科医になったきっかけや世代の中間を担う立場としての臨床・教育・研究への取り組みや課題感などについてお話しいただきました。
飯田 仁志 先生
(司会進行・福岡大学医学部精神医学教室 講師)
川俣 安史 先生
(獨協医科大学精神神経医学講座 講師)
村岡 寛之 先生
(北里大学医学部精神科学 講師)
「メンタル(精神)というアプローチが難しそうなものに取り組んだほうが面白さ、やりがいがあり、成長にもつながる」(飯田先生)
精神科医になったきっかけとやりがい
飯田 最初に、読者の方々への紹介も兼ねて、精神科医になったきっかけをお話しいただこうと思います。私は、研修中は外科を志望しており、精神科は一番理解が難しく、楽しさもよくわからない診療科という印象を持っていました。しかし、外科で精神的に良好な状態でないにも関わらず、身体的な回復をもって退院していく症例を数多く診るようになり、「メンタル(精神)という、アプローチが難しそうなものに取り組んだほうが面白さ、やりがいがあり、自分の成長にもつながる」と思い直し、研修途中で精神科に変更したという経緯があります。精神力動や精神療法などを大事にする医局であったことから母校である福岡大学の精神科に入局しました。
村岡 私は大学卒業後、救急科に進むことを考えており、精神科医になるつもりはありませんでした。救急の有名な病院で初期研修を終えたのですが、私の父が精神科医であった縁で「面白いのかな」と興味を持ち、東京女子医科大学精神科に入局しました。その後、北里大学に移り、現在に至ります。
川俣 私の略歴は、少々特殊です。薬学部卒業後、薬剤師として精神科病院に2年間勤めました。しかし、「医師になりたい」という気持ちを抑えきれず、獨協医科大学に入学し、2013年に卒業しました。研修中は脳神経内科に惹かれていましたが、精神科で指導医の先生に統合失調症症例への薬剤選択を褒められ、実際に改善した成功体験も相まって、精神科医の道を選びました。
飯田 お2人とも精神科医としてこれまで、多くの患者さんに向き合ってきたと思います。私自身は小児から高齢者まで幅広い患者さんを診る中で、いろいろな人の人生が垣間見え、患者さんの人生の中で自分が役に立つことを探し続けられる分野だとやりがいを感じています。お2人はいかがでしょうか。
村岡 私は東京女子医科大学在籍時、急性期病棟の患者さんを数多く診る機会に恵まれたことで、臨床が好きになりました。EBM(Evidence-Based Medicine)に則るからこそ、患者さんに寄り添えるという考えで、日々診療に取り組んでいます。
川俣 私は大学を出て精神科単科病院で診療をしていた時期もあるのですが、多くの患者さんに向き合える一方、検査や治療の選択肢があまり多くないことを実感し、それが大学に戻るきっかけの一つとなりました。一部の治療薬や電気痙攣療法が使えないときは、少々寂しく感じたものです。
「実際に手を動かしてもらうなど、研究を毛嫌いされないような工夫をしています」(村岡先生)
若手医師に研究をすすめるきっかけづくり~苦労と工夫
飯田 私たちは大学の医局運営にあたり、上長の意向を汲みつつ後輩の先生方を育てる役割を担う中間世代です。最近、「大学にいればさまざまな症例が経験できる」という視点で大学病院を選ぶ医師が増えているように感じます。裏を返すと、研究目的の医師ばかりが大学にいるわけではないということではないでしょうか。一方で私たちより上の世代の先生方を中心に、「大学は研究する場所」という考えは根強くあり、このあたりに世代間のギャップがあります。自身で研究するようになると、後輩の先生にも自信をもって「研究したほうがいい」と伝えられますが、研究を促すきっかけ作りが難しいと感じます。
村岡 基礎研究は敬遠されがちですが、臨床は初期研修から接しているので、臨床研究は取り組みやすいのではないでしょうか。北里大学では現在、臨床データベースを構築中であり、このデータベースを誰でも解析できるようにして、学会発表につなげたいと考えています。実際に手を動かしてもらうと「研究はかしこまらなくてもいいのですね」と言った後輩の先生がいました。研究を毛嫌いされないような工夫が必要です。
飯田 福岡大学でもデータベースの導入を検討中です。実際に手を動かせるものがあると、研究に取り組む良いきっかけになりそうです。
川俣 診察で疑問に思ったことを文献で調べるとケースレポートにつながるので、まずはそこから臨床研究を始めるのが良いと思います。若い世代の先生方の中には、臨床と研究を分けて考えている人もいますが、「文献を調べたら、それはもう研究です。調べて分からなければ、その疑問を研究テーマにすると良いと思います」と伝えると、研究が身近に感じられるようで、研究に前向きになる先生も少なくありません。
飯田 臨床疑問を研究につなげるのはスムーズですね。
川俣 「私は臨床だけ学びたい」、言い換えると「臨床と研究は別のもの」と考える方もいますから、その間違いは指摘しても良いと思います。
また、若手の研究離れは確かにあるので、楽しさを感じてもらう方策が重要です。獨協医科大学での取り組みのひとつが、学会への参加です。以前、当科では発表機会がない限り学会参加を医局として補助していませんでしたが、今は年1回、勉強になりそうな学会であれば参加費と旅費を補助して参加を励行しています。学会に参加すると刺激を受けるようで、自然と研究に興味を抱く方が現れます。
「最近、教育と研究を縦割りにせず、リンクさせることが重要だと気づきました」(川俣先生)
臨床・教育・研究をリンクさせて業績につなぎ
医学生・若手医師のポテンシャルを伸ばすことが重要
飯田 先生方は、学生教育にどのように携わっていますか。私は4年次と6年次の講義を担当しており、ベッドサイドでの教育も大切だと考えています。
村岡 私も、講義を数コマ担当しています。病棟長でもあるので、学生と患者さんがしっかり話ができているかといった医療面の評価をMini-CEX(mini-clinical Evaluation Exercise:簡易版臨床能力評価法)で行っています。講義とベッドサイド・ラーニング(Bed Side Learning:BSL)、どちらも大切ですね。
飯田 福岡大学では、2年生のときに1か月間、研究室配属という実習期間があります。当科ではデータ集積・解析を一緒に行っています。
川俣 獨協医科大学では、精神科を回る臨床実習、いわゆるポリクリの医学生に「EBM実習」を行っています。この実習では、学生3~4人が1グループとなり、担当患者さんに関係するEBMや臨床疑問の回答となり得る論文を調べて発表したりしています。その中にはケースレポートになりそうな斬新な文献的考察もあり、そこから学会発表に発展することもあります。この経験は業績につながりますから、臨床から研究への好循環が生まれます。
村岡 素晴らしい取り組みです。私たち中間世代の負担も少ない印象です。北里大学では学生教育係である助教の先生がしっかりフォローしていますが、教育と研究のリンクはできていないので、意識したいですね。
川俣 無理なく・ロスなく循環させていく、サステナブルな方法だと思います。最近、教育と研究を縦割りにせず、リンクさせることが重要だと気づきました。学生は斬新なアイデアで臨床疑問を立てることがあり、発表で私たち指導側も知らない、興味深い論文が紹介されることもあります。教えた分だけ私たちも得るものがあると思うと、教育が苦ではなくなります。
飯田 教育と研究をリンクさせる考えは、応用が利きそうです。私たちの上長や学会等を主導・運営されている先生方は、教育と研究、そして臨床のリンクを効率良く行ってきた方々だと思います。自分が後輩の先生方を教育・指導してみて、上の先生方がいかに思慮深く物事を行っていたのがよく分かります。私たちは上の先生方から学びつつ、「臨床・教育・研究のリンク」というコンセプトを磨き上げ、後輩の先生方にバトンを渡さなければならないと思います。(後編へ続く)
<プロフィール>
飯田 仁志 先生
福岡大学医学部精神医学教室 講師
2009年、福岡大学医学部卒業。久留米大学病院での研修を経て、福岡大学医学部精神医学教室に入局。助教、医局長を経て、2023年より現職。専門分野は精神医学全般、老年精神医学。日本精神神経学会精神科専門医・指導医、日本老年精神医学会専門医・指導医、日本認知症学会専門医・指導医、精神保健指定医
川俣 安史 先生
獨協医科大学精神神経医学講座 講師
2005年、東京理科大学薬学部卒業後、精神科単科病院に2年間勤務。その後、獨協医科大学に入学、2013年卒業。学内助教を経て、2023年より現職。専門分野は薬物治療。日本精神神経学会専門医・指導医、日本総合病院精神医学会一般病院連携精神医学専門医・指導医、日本臨床精神神経薬理学会専門医、日本老年精神医学会専門医・指導医、精神保健指定医、日本医師会認定産業
村岡 寛之 先生
北里大学医学部精神科学 講師
2009年、日本医科大学卒業。みなと赤十字病院にて経験を積んだ後、東京女子医科大学精神科に入局。助教、准講師を経て、2022年より北里大学医学部精神科学に移籍、現職。専門分野は精神薬理。日本精神神経学会専門医、日本精神神経学会精神科指導医、精神保健指定医、精神科薬物療法専門医
座談会取材、撮影:ルンドベック・ジャパン Progress in Mind Japan RC
取材日:2024年12月1日
場所:青山ローズガーデンスタジオ(東京都港区)
Progress in Mind Japan Resource Centerは、会員の皆様が安心して自由に意見交換できる場を提供することを目指しています。
本コンテンツに登場する先生方には、Progress in Mind Japan Resource CenterのWebコンテンツ用の取材であることを事前にご承諾いただいたうえで、弊社が事前に用意したテーマに沿ってご意見・ご見解を自由にお話しいただき、可能な限りそのまま掲載しています。
お話の内容は、すべての患者様や医療従事者に当てはまるものではなく、またそれらの内容は弊社の公式見解として保証するものではありません。