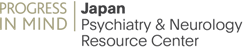うつ病診療の発展を目指して 治療抵抗性うつ病の臨床と研究 精神医学クローズアップVol.22
髙橋 隼 先生
(大阪大学大学院医学系研究科 精神医学教室 講師)
うつ病治療において、抗うつ薬治療に反応を示さない「治療抵抗性」を示す患者が一定の割合で存在し臨床的課題となっています。こうした状況を受けて2019年には治療抵抗性うつ病に対する経頭蓋磁気刺激(Transcranial Magnetic Stimulation : TMS)療法が保険収載されるなどの動きもあります。
本稿では、抗うつ薬以外の治療アプローチの1つであるニューロモデュレーションのトップランナーのお1人である髙橋隼先生に、治療抵抗性うつ病の治療とニューロモデュレーション療法の現状について伺うとともに、所属施設の枠を超えた取り組みについてもお話しいただきました。
治療抵抗性うつ病に対するアプローチとは
―はじめに、「治療抵抗性うつ病」について教えてください。
この数年、やはりうつ病の治療は難しいなといろいろ感じるところがあります。もともとキャリアの多くを大学病院で過ごしてきたので他の医療機関で治療が奏功せずに紹介をいただいた患者さんを診る機会が多かったのですが、2019年にうつ病に対する経頭蓋磁気刺激(Transcranial Magnetic Stimulation : TMS)※療法1が保険収載されて以降、治療抵抗性の患者さんを診療する機会がさらに増えました。
抗うつ薬の初期治療への治療反応が不十分であったうつ病患者を対象に実施された米国の大規模研究STAR*D (Sequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression) Studyでは、変薬や増強療法、精神療法などを試みても最終的に3分の1の患者さんは寛解に至らなかったという結果が出ています。さらに、一度寛解しても良い状態をキープしている人はもっと少ないことが分かっています2。
※経頭蓋磁気刺激(Transcranial Magnetic Stimulation: TMS)
パルス磁場によって渦電流を誘導し皮質ニューロンを刺激することで、非侵襲的に皮質や皮質下の活動を変化させる治療法。
「多角的に患者さんを診て、治療を難しくしている要因を見つけることが大切だと実感しています」
―治療抵抗性うつ病の場合の対処法ついて、先生のお考えをお聞かせください。
まず、抗うつ薬については、短期間のうちに何回も薬を変更しないことをおすすめしたいです。STAR*D Studyの結果でも3剤目以降は寛解率が大きく下がる2ことから、短期間での薬剤変更の繰り返しは推奨されないことが示されています。
早く良くなってほしいとの思いからアクションをとりたくなる気持ちも分かりますし、患者さんから「薬があまり効いていないので変えてほしい」と言われたときに、「もう少しこの薬で粘ってみましょう」と言うのはエネルギーが要ることも分かります。それでも、医療者側は薬を次々に変えても奏効率はあがってこない知見があることを理解したうえで、服薬状況や副作用が出ていないかに注意しながら、患者さんに治療反応をじっくりと待つ有用性についてご説明することが重要ではないかと思います。
どれくらいの期間が十分かと一概に示すのは難しいですが、個人的には少なくとも8週間以上、できれば12週間くらいは効果が出てこないか待ちたい気持ちで治療しています。
もう1つは、適正な使用量で十分な期間の薬物療法を行ったにも関わらず効果がみられなかった場合は、「なぜ効果が出ないのか」を検討することを心がけています。
私がrTMS療法に携わっている浅香山病院では、ほぼ全例が入院でrTMS療法を受けており、1人の患者さんに複数の医師と多職種の医療者が関わって治療に当たります。そのため、外来診療だけでは気づきにくい患者さんの生活背景を知ることができたり、医師の中でも患者さんの見立てが異なることに気づいたりします。思い返せば、このような治療体制は精神科領域ではあまり見られないのではないでしょうか。
治療抵抗性を示す場合、その人のパーソナリティやこれまでの環境が関係して難治化していることもありますが、現在の食事や睡眠などの生活習慣などが影響していることもあり、うつ病治療と同時に体のケアを行うと症状が改善することも少なくありません。このように、多角的に理由を探っていくと何をすべきかが見えてきて、治療を前に進めることができます。
うつ病におけるニューロモデュレーションの現状
―ニューロモデュレーションをご専門にされたきっかけを教えてください。
精神科医になりたてのときに教室でTMSを利用した研究がされていて、自分自身もTMSを受けたことがありました。運動野という手を動かす領域に磁気刺激を行うと、自分の手が意思とは関係なくパーンと動き、「本当に脳に介入しているんだ、これはすごい」と思った経験が根底にあります。
精神科は他の領域と違って手術をするわけではありませんが、rTMSや電気けいれん療法(Electroconvulsive Therapy:ECT)をはじめとするニューロモデュレーションはダイレクトに脳に介入している感覚があり、そこに惹かれました。また、こうした治療を必要とする人は、薬など他の治療が効かなくて紹介されてきた人が多いという点にもやりがいを感じ、現在に至っています。
―rTMS療法の普及状況について教えてください。
日本では現在、約70施設がrTMSを保険診療で提供しています3。2023年に「反復経頭蓋磁気刺激(rTMS)適正使用指針」(日本精神神経学会作成)が改訂され精神科専門医以外の医師や医療スタッフが担う役割が拡充されるとともに、2024年度診療報酬改定では保険点数が引き上げられる4など、普及に向けて良い方向には動いているのですが、地域偏在が大きく、治療を必要とする患者さんが遅滞なく診療を受けられる環境とは言えないのが現状です。患者さんの認知度はまだまだ低いですし、精神科専門医であっても、rTMSとはどのような治療で、どの程度効果があるかを詳しく知らない先生方もいらっしゃると思います。
rTMSを普及させ均てん化していくには、この療法に携わっている私たちがしっかりしたデータを出し情報を発信することで、治療抵抗性で苦しんでいる方にrTMSという選択肢があることを医療従事者や患者さんに伝えたいと考えています。
「異なる状況の中で集められたデータは、リアルワールドデータとして価値がある」
所属施設の枠を超えた活動
―髙橋先生が立ち上げた研究会についてお話しいただけますか。
rTMSが保険適用となり、臨床データが得られるようになりましたが、単一施設では症例数が少なく、経験の蓄積にも限界があります。そうした現状をどうにかしたいと思っていたときに、以前から知り合いだった関西医科大学精神神経科学講座の池田俊一郎先生が「複数の医療施設で一緒に取り組んだらいいのではないか」と発案してくれたのが研究会(関西TMSネットワーク)を企画するきっかけとなりました。そこで大阪近辺の施設の先生に声を掛けて体制を整えていきました。関西エリアでは大阪医科薬科大学が一番早くrTMS保険診療を導入されたのですが、引き続いてrTMS療法を導入した医療機関で集まって、当初は運用の仕方やrTMS療法を適応する患者さん像などを共有していました。その後、3つの大学病院(大阪医科薬科大学、関西医科大学、和歌山県立医科大学)と2つの精神科病院(浅香山病院、阪南病院)で診療データを蓄積する研究も立ち上げました。
本研究会の活動では、同じ関西エリアであっても大学病院、精神科病院などの違いや、その施設が担当している医療圏によってもそれぞれが持っている医療資源や提供している医療のアプローチが異なることを感じました。さまざまな状況の中で集められたデータは、リアルワールドのデータとして価値があると思っています。そこで、100症例ほどが集まったところで大阪医科薬科大学神経精神医学教室の今津伸一先生が筆頭著者でデータを解析して論文にまとめて下さり、2024年にAsian Journal of Psychiatry誌に発表しました5。かねてより、論文タイトルに研究会の名称を入れたいという思いがあったのですが、本論文で実現することができました。インターネットで「Kansai TMS network」と検索すると、この論文がヒットするのがうれしかったですね。各施設でrTMS療法を立ち上げていくときにいろいろな悩みを話し合ったりしていた活動を形に残すことができたので、とても気に入っている論文です。
―所属施設の枠を超えて協業する活動においての苦労や、振り返っての感想などをお聞かせください。
私自身はそれほど苦労したことはなく、むしろ自分の施設だけでは分からなかった視点や行動につながる力が得られてありがたい経験ばかりでした。誰かから指示されたのではなく、「こういうことがやりたい」という思いのもとに自然発生的に立ち上がった活動だったからこそ、無理なく、うまく機能したのだと思います。周りの方々に恵まれていました。
もう1つ、研究会を立ち上げて良かったと感じる点は、研究をベースにしたことです。研究であれば計画書をつくるなかで研究内容の枠組みが決まりますし、目的も明確にしやすいからです。臨床だけではなく研究としてデータを集積すること、そしてそれを論文にすることを意識して活動することが大切だと考えています。小さな論文でも活動を共にした皆にとっての実績となりますし、社会に還元するやりがいを感じることで研究継続へのモチベーションにもつながります。
―今後、どのような研究に取り組みたいとお考えでしょうか。
うつ病治療のなかでrTMSをどのように使ったらよいのかを引き続き検討していくとともに、この治療法の活用を拡大していくための研究を視野に入れています。もちろん臨床研究は1人では進められないので、共通の目的を持つ人たちと協力しながら、この分野の機運を高める一助になれればと考えています。
「日頃感じている思いを口に出して、一緒に動いてくれる仲間を持つことが大切」
うつ病診療の発展のために伝えたいこと
―最後に、読者に対するメッセージをいただけますか。
私は40代半ばになるのですが、この世代は、管理業務だけでなく現場で患者さんを診ているという、大変ではありますが、いい意味で楽しめる立場であるといえるのではないでしょうか。学会の委員会活動でrTMS適正使用指針の改訂に携わりましたが、自分が現場で取り組んでいる医療をより良いものにできる活動に関われたこともうれしかったですね。
医療従事者はそれぞれに「こうしてみたい」「こうすればもっとよくなるのではないか」と思っていることがあると思います。私の場合は、数人が集まってそういう思いをカジュアルに話しているうちに「これぐらいなら実現できるのでは?」と話が具体的に動き出した感じでした。日頃感じている思いを口に出して、一緒に動いてくれる仲間がいれば、少しずつでも状況を変えていくことはできます。それには、施設の枠を超えてフラットに付き合えるつながりを持つことが大事だと思っています。
取材/撮影:ルンドベック・ジャパン Progress in Mind Japan RC
取材日:2025年3月28日
取材場所: 大阪大学医学部附属病院(大阪府吹田市)
Progress in Mind Japan Resource Centerは、会員の皆様が安心して自由に意見交換できる場を提供することを目指しています。
本コンテンツに登場する先生方には、Progress in Mind Japan Resource CenterのWebコンテンツ用の取材であることを事前にご承諾いただいたうえで、弊社が事前に用意したテーマに沿ってご意見・ご見解を自由にお話しいただき、可能な限りそのまま掲載しています。
お話の内容は、すべての患者様や医療従事者に当てはまるものではなく、またそれらの内容は弊社の公式見解として保証するものではありません。