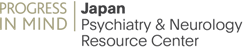コラム 詩人・精神科医として独自の視点で現代社会と医療に向き合い、チャレンジを続ける
尾久 守侑 先生(慶應義塾大学医学部 精神・神経科学教室 特任助教、国立病院機構下総精神医療センター)
詩人であり、精神科医である尾久守侑(おぎゅうかみゆ)先生は、「個」、すなわち1人の人間としての感覚を大切にして現代社会と医療に向き合い、さまざまな活動に従事しています。医師としては、一般内科の外来診療にも携わっており、精神科医として培ってきた経験をもとに、思春期の方も含む患者さんの心身をトータルに診る医療に意欲的に取り組んでいます。尾久先生に、詩を書き始めた頃から現在までを振り返っていただき、独自の臨床実践のなかで深めてきた社会や医療に対する関心、それに向けて取り組んできたことについてお話を伺いました。
―詩を書くようになったきっかけを教えてください。
もともと本を読むのが好きで、高校生の頃とかって、小説とか詩とか書きたいと思いがちだと思うんですが、そういうノリで書いたのが最初でしたね。一人で授業中に書いたりしてました。でも受験が忙しかったので、一度書くのをやめたんです。高校生のときは勉強で校内1位というのがアイデンティティーだったのですが、大学生になったら、みんな賢いし優秀だし、勉強をがんばっても1番とかになれないし、ちょっとアイデンティティーが揺らぐような感覚になって、そういうときに思い出したんです、詩があったと。それで、詩の雑誌に投稿し始めたという感じです。
―精神科医と詩人の2つの顔をお持ちですが、精神科医になられてから現在までを振り返って、詩人としての経験、精神科医としての経験が相互に影響していることを感じますか。
それぞれ別にやっていたことではあるのですが、最初の頃は、例えば“精神科医療の詩”とか書いたらちょっと寒いなと思い、そういうのは書かないようにしようとか決めてやっていました。でも、やっていくうちに混然一体となってきたというか、自分のなかであまり区別がなくなってきたようなところがありますね。そんなに違うことをしているという感覚があまりないです。
診療をずっとやっていると、手痛い失敗があったりとか、傷ついたりとかがあって、成熟というか、少しずつ自分が更新されるわけです。そういう部分は詩に反映されるようにはなってるかもしれないですね。
―最近、個人の更新を実感したエピソードについて教えてください。
精神分析家のサールズの書籍『逆転移』1を読んで、「軽蔑」について考えるようになりました。その書籍には統合失調症の患者さんを治療している医師が、献身的な関わりをしているときには、自分が献身的な医師であることを維持するために、患者さんを未熟な自我機能のままにしておこうと無意識にしてしまうことがあるという話が書かれています。
そういう「軽蔑」は、診療だけではなくて、例えば習いごととか部活とか、結構ふだんからあると思うんですね。
ついやってしまいがちなのですが、医師の診療のなかで「俺に付いてこい」みたいな態度は、ある意味で患者さんの主権を奪っているようなところがあると感じています。パーソナリティ同士が響き合って、患者さんのほうも「付いていきたいです」となったりすると、うまくいっているかのように思ってしまいがちですが、そこで「はっ」と気付くことが増えました。
―患者さん中心の医療を、医療従事者が患者さんと共に目指すために様々な取り組みがなされていますが、そういった取り組みと近いと考えて良いのでしょうか。
近いとは思うんですけど、横目にそういった取り組みを見ていると、やっぱり医者が新しい概念を持ってきて、どうですか?と提案していることと構造上は変わりないんじゃないかなとは思ってしまいます。
そういった提案をすると、患者さんが言葉ではないところで、都度「それは違う」と意思を発するわけです。次の外来に来なかったりとか、遅刻したりとか、そういうところに表れてきます。「薬を飲もうと思ったけど忘れちゃいました」とか、「薬100日分余ってます」とかいうのも同じですね。そこまでキャッチする意識がないと、患者中心にはならないのではないかと思います。
―患者さんが自分の内的に思っていることに気付いてもらうためのアプローチが重要ですね。
例えば、患者さんが「薬を飲みます」と言っていて、意識としては
飲みたくても、無意識的にはあまり飲みたくないということが分かれば「そもそも、薬飲むの、あんまりピンと来てない?」みたいな感じで訊けるわけです。
思春期の方も全くそうなのですが、言葉にならないというか、できないことがあるわけですが、そういう気持ちに言葉を付けてあげる。本人の自弁性を育てるというか、自分の内的に思っていることに気付くきっかけとなるようにすることが大事ですね。
―大学病院などでの精神科診療とは別に、総合病院で一般内科の外来診療に携わっていますね。そこでは、思春期の患者さんの診療を行うことがあると聞きました。
2016年から総合病院の非常勤として内科外来に携わっています。1日で約50~70人を診ていて、そのうち新患は約20人です。そのなかで、思春期の患者さんやメンタル不調の方を診ることがあります。

―内科外来における思春期の患者さんへの診療経験を振り返って、精神科診療が役に立ったことや精神科外来だけでは気付かなかったことを教えてください。
割と最初に内科を受診するということですかね。不登校とかも、始めに身体症状が起こりやすいといわれています。ふだん、精神科の外来では、発症してからだいぶ時間が経った患者さんを診ているのですが、かなり問題が込み入ってしまった状態になっていることがしばしばあります。なので、内科に来た時点で拾うことが本当に大事だと思います。
また、子どものほうが大人が擦り寄ってくる雰囲気に敏感です。「この人に話しても意味ないわ」、「分かんないな、この人」というように、患者さんが選ぶということがあると思いますね。
―思春期の患者さんとの関係づくりのコツを教えてください。
今の私の場合、思春期の患者さんとは年齢が近くはないけど、割と若い話題に付いていけるので、そういう話をして、お兄さん的な感じで手を組もうって感じでやっています。信頼してもらうというか、「この人ちょっと違うな」とか、「親とか学校の先生と違う」というような存在として、まずは認識されることが重要だと思います。ただ、例えば私が60歳になってそのやり方をしたらおかしいので、うまくいかないと思います。やはり都度変わっていくというか、自分がどう見られているかとか、どういう人間としてその場にいるのかを意識して振る舞うということは大事だという気がします。
―思春期の患者さんに、SNSの利用状況などについて聞くことはありますか。
何か情報の一つではあると思っていて、この子がSNSをそんな使い方しているのかとわかったり、見るだけだと思っていたら、実はすごく頻繁に投稿しているとわかったりすることがあります。
―内科外来を長く続けられているのは、身体症状・疾患を心理社会的な背景から診ていくことの重要性も感じているからでしょうか。
身体なのか心なのか、あるいは病気か病気じゃないのかといった境界線を診ることが、自分の専門性なのかなと思うところがあります。あいまいなところにいる方は興味深いです。その一環として内科外来を長く続けているという感じですね。そういうところは当然、エビデンスとかはないですし、より答えがないので、臨床的に模索していくということが自分の研究だと思うところはあります。
―医療従事者向けの書籍3編2-4が上梓されていますが、こうした背景が関係しているのでしょうか。
今、エビデンス一辺倒で苦しいという医師は少なくないと思うんですよね。そういうのだけで診療をやっていると当然、行き詰まります。ただ、その先はあまり言語化されてないわけで、そこを記した書籍があれば楽になる人はいるのではないかと思っていました。
書籍の内容は、1980年代の教科書とかに書いてあったものです。あるとき、古い教科書が、今の教科書にはない臨床知が記されている宝の山に見えたんですね。それらを全然習っていなかった、専門医にまでなったのに何も知らなかったと。リバイバルではないんですけど、文字に残してちゃんと伝えたほうが良いなと思って書いたところは大きいです。こうした臨床知を内面化した精神科医が増えたらいいなと思っています。
取材/撮影:ルンドベック・ジャパン Progress in Mind Japan RC
取材日:2023年8月1日
取材場所:ルンドベック・ジャパン株式会社
Progress in Mind Japan Resource Centerは、会員の皆様が安心して自由に意見交換できる場を提供することを目指しています。
本コンテンツに登場する先生方には、Progress in Mind Japan Resource CenterのWebコンテンツ用の取材であることを事前にご承諾いただいたうえで、弊社が事前に用意したテーマに沿ってご意見・ご見解を自由にお話しいただき、可能な限りそのまま掲載しています。
お話の内容は、すべての患者様や医療従事者に当てはまるものではなく、またそれらの内容は弊社の公式見解として保証するものではありません。