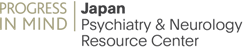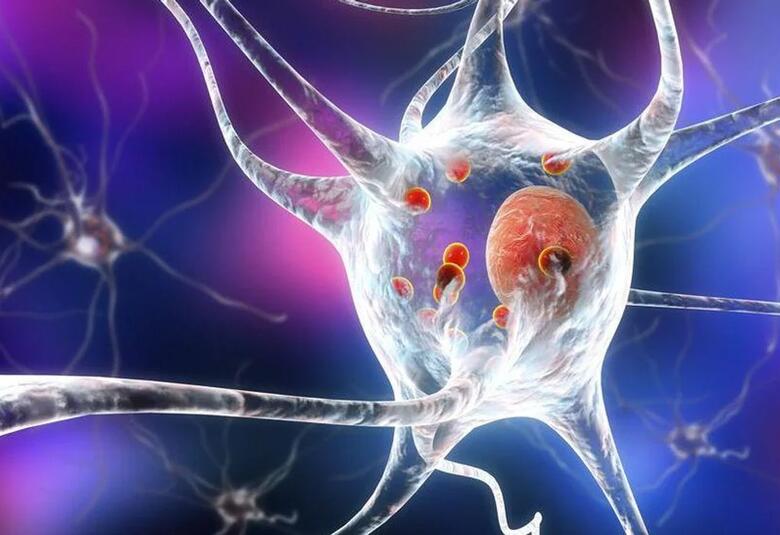炎症記憶は皮膚細胞や神経細胞でも保持されている可能性、レビュー論文で示唆
免疫系以外の組織でも多くの細胞が「炎症記憶」を保持しており、組織の機能にさまざまな影響を及ぼしていることが、「Nature」2022年7月14日号掲載のレビュー論文でまとめられた1。米ニューヨーク大学ランゴン・ヘルスのShruti Naikらは今回のレビューで、炎症記憶の分子学的機序の解明に関する最新の研究結果を総括。エピジェネティックな炎症記憶は炎症性疾患やがん、アルツハイマー病のリスクを上昇させる可能性もあると考察した。
ヒトの免疫系では、抗原特異的なリンパ球のサブセットが遭遇した病原体を記憶し、再感染時に迅速に対処できるよう備えている(獲得免疫)2。一方で各組織では、抗原への最初の防御応答と炎症から回復した後、さまざまな細胞が非特異的な炎症記憶を保持し、感受性を高めて異物に対処する準備状態を維持していることが、近年明らかになってきたとNaikらは説明している。
炎症記憶の分野は、2007年、非特異的な炎症記憶が核内に存在し、エピジェネティックなレベルで伝達されることを報告した画期的な研究から始まった。同研究では、マクロファージのToll様受容体を微生物ペプチドに曝露後、クロマチン修飾の持続的変化が生じたことから、免疫記憶が自然免疫細胞にも存在することが判明3。2011年には、この自然免疫細胞の炎症記憶に基づく反応は、訓練免疫(trained immunity)と名付けられた4。それ以降、炎症記憶は免疫系以外のさまざまな組織の細胞にも存在することが相次ぎ明らかにされてきた。例えばNaikらの2017年の研究では5、皮膚の上皮幹細胞と前駆細胞が炎症記憶を持ち、組織の機能的適応に影響することを示している。
Naikらの総括によると、自然免疫細胞の炎症記憶は、免疫プライミングまたは訓練免疫の二次応答による増強、または寛容による減弱に基づいて適切に維持される5,6。また、非免疫系の組織細胞は、免疫細胞から主にサイトカインを介したシグナル伝達を受けているが7,8、それに加えて微生物による刺激を直接感知し、エピジェネティックな炎症記憶を呈すると考えられる。最新のマウス研究では8、妊娠中の感染が胎仔の腸の上皮細胞の炎症記憶を惹起し、その影響が仔の成人期まで持続することも示された。こうした炎症記憶の分子学的機序は、最初期の研究以来、クロマチンやヒストン修飾に関連するとされており、記憶の確立や想起などの仕組みも含めて詳細が解明されつつある。
しかし、「長期的に炎症が累積し、炎症記憶を適切に維持できなくなれば、炎症性疾患やがんなどの発症につながり得る」とNaikらは指摘。乾癬9や炎症性腸疾患10,11、 COVID-19後遺症12などでその潜在的証拠を挙げたほか、心臓発作後の全身炎症により乳がん罹患リスクが高まること13、急性膵炎14,15により腺房細胞のがん化リスクが高まることを示唆する研究結果を提示した。
さらに神経細胞も、免疫細胞や組織幹細胞と同様に寿命が長く、エピジェネティックな記憶を長期間保持しやすいと考えられるという。実際、複数のマウス研究から16-19、妊娠中の感染や食生活、ストレスに起因した炎症による腸内細菌叢異常が胎仔の脳にエピジェネティックな記憶を惹起し、神経発達障害に関連する可能性があることが分かっており、これには脳の常在マクロファージであるミクログリアが関与する可能性が示唆されているという。さらに、島皮質の神経細胞が腸の炎症を記憶するとの報告20があるほか、アルツハイマー病は炎症やミクログリアの機能不全と関連するとのヒトおよびマウス研究の結果が示されており21、この領域は注視すべきだとした。
Naikらは「直近5年間に行われた多数の研究から、寿命の長い組織細胞は経験を記憶しており、有益性や有害性をもたらすことが分かってきた。このような細胞の記憶を制御して組織の反応を調整できれば、健康増進や疾患抑制が可能になるかもしれない。しかしそのためには、細胞ごとに多様な刺激で生じる各状況に対応した、『ヒト細胞アトラス』計画さながらの詳細なマップが必要となるだろう」と、結論を述べている。(編集協力HealthDay)
Copyright © 2023 Lundbeck Japan. All rights reserved.