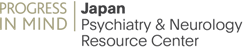小精神療法の核は「患者を助けたい」という医療者の素朴な愛情―どの精神療法家にとってもそれは同じと思います。
小精神療法の核は「患者を助けたい」という医療者の素朴な愛情―どの精神療法家にとってもそれは同じと思います。
なぜ私は、精神科医になると決心したのか。敢えてこれを選んだのはなぜだったか? 小精神療法の歴史を語ろうとすると、どうしてもこのあたりまで遡らなければならないように思うのです。すでに旧制高校の頃からオマセな友人にひっぱられて、フロイト*aやマルクス*bをかじり、医学部志望のくせにクラシックや演劇にも少なからぬ興味を持っていました。
医学生になってからは多少こうした偏向ぶりは是正されましたが、1年が過ぎたときに友人の1人が「自分は医学部には合わないと思うので」と言って法学部へ転科しました。開業医の子息でしたが、父君は反対しなかったそうです。
医学部の3年生か4年生のときに、医学生が編案する学内用の小冊子にたまたま精神科を特集する号が編まれ、村上仁先生*cと満田久敏先生*dという両巨頭の論文が転載され、ホットな対決をあおるような解説が附されていました。この特集によって1年間怠け者だった私は一挙に覚醒しました。その後は、御迷惑も顧みず精神医学教室に入り浸り、その延長上で入局を許されます。
私と同級の精神科入局希望者は3名にすぎませんでした。しかしその翌年には11名が入局しました。これは教授が新任になったからでした。
勇んで入局したものの、いろいろ「体験」がありました。6つあった病棟のうちの2つの重症閉鎖病棟には独特の「臭気」があって、病棟へ行く元気をなくさせました。いろいろ考えて選んだ「精神科」だったのに、「こんなことで初志を貫徹しないなんて」と考え込みました。辞めなくてよかった、と思ったのは、後に新しい病院が続々と建てられるや、この臭気は完全になくなったからです。
同じ頃、プラスの経験もありました。女性の重症病棟を始めて訪れた時のことです。ヒステリー*eの中年の女性患者が若い看護師の介護の仕方に不満らしく、なかなか食事をしないで困らせている場面に出くわしました。私は間髪を入れず、看護師に代わり、 食事の介助をしました。一瞬患者さんは戸惑いを見せましたが、後は素直に私の介助を受け入れました。
これを傍で見ていた婦長さんが「精神科医はこれでなくちゃあ」と褒めてくれました。私には姉妹がいましたので、女性へのこの種の接近はごく当たり前のことだったのですが、たしかに当時の男性医師はそうした行為はしなかったようです。それどころか、病棟へ再三足を運ぶということさえなく、運んでも長話をすることはまったくありませんでした。そもそも、ほとんどの入院患者が統合失調症で、カルテにもドイツ語で短い単語が2つ3つ書かれているだけでした。薬物療法が始まる以前の病棟のことです。
重症病棟の男性看護師は今のように教育を受けていなかったので、目に余る行動が随所に見られました。若い新米の医師が、中年から初老の男性看護師にたまには声を荒げて説教する。あまり見よい光景ではないと思いつつ、苦言を呈しました。そのうち看護師の中から私に手紙をくれて、質問してくれる人も出てきました。できるだけ丁寧に返事し、相手もそのことを多とするようになりました。こういうことは後にも先にもなかったと。
他方、受け持ちの入院患者さんはいろいろと増えましたが、当時は、認可された治療薬もなく、限られた治療手段ではなかなか上手くできません。それでも狭い運動場で「三角ベース(野球を簡素化した子供の遊びの一種)」をしたりすると、見違えるほど患者さんが自然な感情や動作を見せるので不思議でした。この時ばかりは若い看護師も生き生きした表情で患者さんに応じていて、ほほえましい光景でした。この経験はやがて運動療法、開放病棟へとつながります。統合失調症はけっこう複雑な構造の病気だと直観したのです。
そしてやがて薬物療法の時代の幕が開くのです。

次ページ
「薬の登場と発展、他領域からの精神科診療への参入により、精神医学の在り方は大きく変わった―その現場に立ち会えたことはとても幸運だったと思います。」へ
注釈
*a
ジークムント・フロイト(オーストリアの心理学者、精神科医)
*b
カール・マルクス(ドイツの哲学者・経済学者・革命家)
*c
精神科医(1910-2000)。京都大学名誉教授。
*d
精神科医(1910-1979)。大阪医科大学名誉教授。
*e
神経症の一種であり、精神医学において転換症状と解離症状を主とする状態に分かれて研究された過去の呼称(参考:小此木啓吾、大野 裕、 深津千賀子 『心の臨床家のための必携精神医学ハンドブック』創元社、1998年、167-169頁。ISBN 4-422-11205-8)。
取材/撮影:ルンドベック・ジャパン Progress in Mind Japan RC
取材日:2022年7月27日(水)
取材場所:ヒルトン名古屋(愛知県名古屋市)
本コンテンツ弊社が事前に用意したテーマに沿ってご意見・ご見解を自由に執筆いただき、可能な限りそのまま掲載しています。お話の内容は、すべての患者様や医療従事者に当てはまるものではなく、またそれらの内容は弊社の公式見解として保証するものではありません。また、記載されている臨床症例は、一部であり、すべての症例が同様な結果を示すわけではありません。