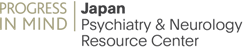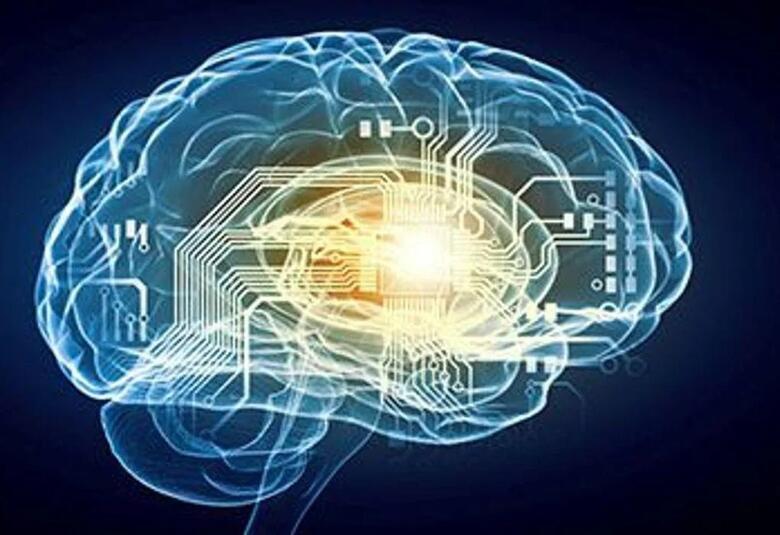体細胞変異の過剰蓄積に神経精神疾患は影響しない可能性
ヒトの脳では体細胞変異が過剰に蓄積されることがあるが、こうした現象は神経精神疾患の発症などとの関係は薄く、加齢により生じている可能性があるという研究結果が、「Science」2022年7月29日号に掲載された1。ただし、胎児期などの初期発生で生じる体細胞変異は自閉症に関連する可能性があることも、本研究では示唆されている。
体細胞変異は、ヒトの初期発生と加齢の過程で自然に発生することが知られているが2-5、その発生頻度や神経精神疾患との関連性は解明されていない。そこで今回、米メイヨー・クリニック Quantitative Health Sciences部門のTaejeong Baeらは、米国内の研究所3施設において、対象者131人(うち定型発達44人、トゥレット障害19人、統合失調症9人、自閉症59人)の死後の脳から、皮質、線条体、海馬の組織検体を採取。組織検体ごとの深度200倍以上の全ゲノムシーケンスや単一細胞シーケンスなどを実施し、脳の体細胞モザイクについて詳しく調べた。
その結果、対象者では1人当たり20~60個の体細胞点変異が確認され、コホート全体の対立遺伝子頻度は1〜10%であることが分かった。対象者のうち7人(約6%)の脳では、100個を超える体細胞変異の過剰蓄積(超変異)が認められた。超変異例は、定型発達2人、トゥレット障害1人、統合失調症3人、自閉症1人であった。なお、体細胞変異の過剰蓄積がない者(非超変異例)では、定型発達群と各神経精神疾患群との間で、体細胞変異の変異量や変異の傾向に違いは見られなかった。
非超変異例では、年齢が上昇しても変異量は増加しなかったことから、変異は初期発生で生じたと考えられた。一方、超変異例は60歳以上(16%)で40歳未満(2%)よりも多く見られ、加齢に伴って増加することが判明した(P=8.2×10^(−3)、χ2検定)。このことから、超変異例の変異は初期発生と加齢の両方で生じたことが示唆された。
超変異例の変異アリル頻度を非超変異例と比べた結果、超変異例における超変異性は、先天性に存在したのではなく、後天性に獲得されたものであることが示唆された。また、個別の変異を見たところ、超変異例3人(定型発達、トゥレット障害、自閉症各1人)の脳において既知のがん関連遺伝子11個が認められ、うち1個(NRAS)は2人の脳から見つかった。超変異例では非超変異例と比較して、がん関連遺伝子の有害な変異が多い傾向があった(P=2.4×10^(−3)、fisher正確確率検定)。さらに一部の超変異例ではクローン増殖の証拠が認められ、超変異性は特定の細胞系統の拡大によって生じた可能性が示唆された。
一方で本研究では、定型発達群と各神経精神疾患群において、こうした体細胞変異がゲノム機能に及ぼす影響も分析した。全ての群で、体細胞変異のうち2~3%はコード領域に、他の6%は調節領域に影響し得る領域に存在していた。自閉症群および統合失調症群の脳において、既知の神経精神疾患に関連するコード領域の変異6個(PCDH15、MTORなど)が認められた。また、自閉症群では対照群と比較して、胎児期の脳で活性化するエンハンサー様領域において、転写因子結合モチーフを作成する変異が過剰であることも分かった(P<10^(−4)、二項検定)。自閉症群で最も目立った変異は、MEIS転写因子に対する16個の結合モチーフに関わるものであり、これら変異と自閉症との関連が示唆された。
著者らは「本研究は、ヒトの脳における体細胞変異の複雑な原因を紐解き、表現型との関連性を明らかにした。体細胞変異の過剰な蓄積は神経精神疾患とは関係なく、加齢に伴って増加した結果と考えられる。一方、自閉症群の脳では初期発生に関わる非コード領域の体細胞変異の過剰も判明した。これらの変異が惹起する遺伝子調節不全は自閉症に関与すると推察され、その機能研究は自閉症の病因を理解する一助になるだろう」と結論付けている。(編集協力HealthDay)
Copyright © 2023 Lundbeck Japan. All rights reserved.