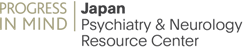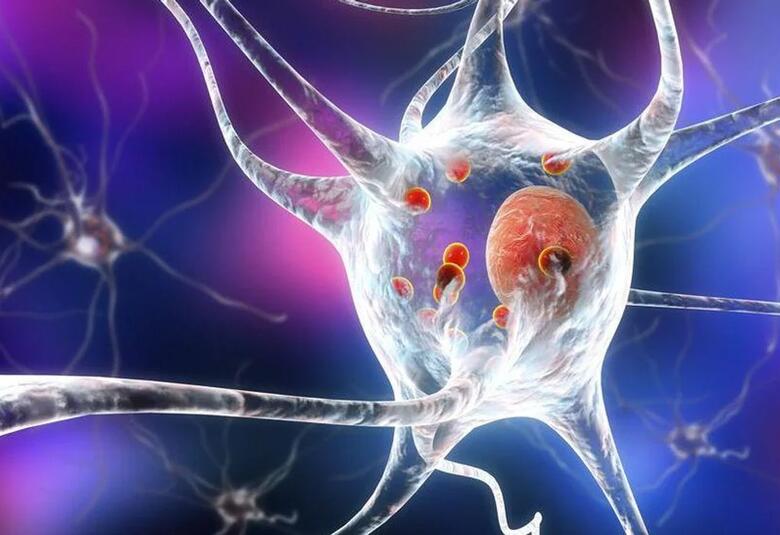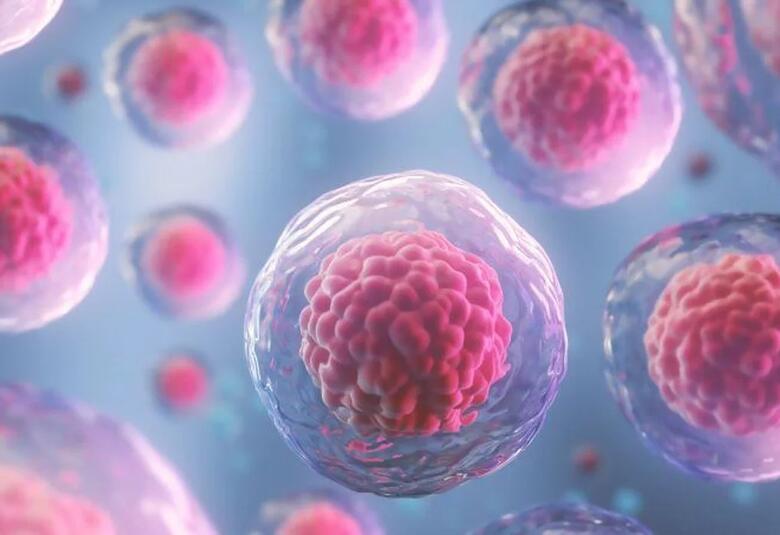ストレス耐性の個人差に報酬系のドパミン神経活動性が関連、マウス研究で判明
ストレスに対する耐性(レジリエンス)の個人差に、ストレス曝露時の行動戦略および脳の報酬系におけるドパミン神経の活動性の違いが影響していることを示唆するマウス研究の結果が、「Nature」2022年11月3日号に掲載された1。
慢性的ストレスは一部の人に抑うつや不安をもたらすが、同じ経験をしてもそうした症状を呈さない人もいる2,3。米プリンストン大学のLindsay Willmoreらは今回、ストレス曝露時の行動戦略とドパミン神経の活動性がこうした個人差に及ぼす影響を検討するため、マウスを使用した研究を行った。
本研究ではまず、マウスに慢性的な社会的敗北ストレスを与え、その影響を個体ごとに定量化した。最初に10日間連続で攻撃的な行動を取るマウス(侵略マウス)と同じケージに入れて社会的敗北ストレスを経験させた後、Social interaction testを用いて社会性行動を測定した。ストレスのない対照マウス(N=22)は、新しい侵略マウスのチャンバーで、51.6±9.65% (平均±s.d.) の時間を過ごした。一方、ストレスマウス(N=32)は40.9±16.7%の時間を過ごし、対照マウスに比べて社会性が低く、個体間のばらつきが大きかった*a。ストレス曝露により侵略マウスのチャンバーで過ごす時間(社交時間)の割合が対照マウスより1標準偏差以上短くなった個体を「ストレス感受性」、そうでない個体を「ストレス耐性」と定義した。
ストレス感受性群とストレス耐性群を比較した結果、ストレス感受性マウスはショ糖嗜好性試験においてアンヘドニア様症状を示し*b、ストレス耐性マウスは、ストレス曝露10日間体重増加が生じる*cといった違いが認められた。また、行動分析では、侵略マウスから攻撃される時間は両群間で同程度だったにもかかわらず、侵略マウスから体を探られる時間は感受性群の方が長く*d、反撃する時間は耐性群の方が長かった*e。さらに接近時の行動戦略として、感受性群では「受動的すくみ」など、耐性群では「反撃」が特徴的に認められた。遠隔時の行動戦略として、感受性群では「回避」、耐性群では「警戒」が特徴的に認められた。こうしたストレス曝露時の行動戦略の差から、各個体がストレス感受性か耐性かを有意に判別できる*fことも示された。
次に、脳の神経活動性がストレス耐性の個体差に及ぼす影響を検討した。具体的には、感受性群と耐性群のマウスに先の実験と同様の社会的敗北ストレスを与え、ファイバーフォトメトリーを用いて、報酬を司る側坐核(NAc)、脅威を司る線条体尾部 (TS)に投射するドパミン神経の活動性を計測した。その結果、全体としてNAcのドパミン活動性は侵略マウスと近づくときに減弱し、離れるときに増強していた。こうした変化は日を重ねるごとに強化され*g、さらにストレス耐性の低い個体ほどその変化が大きかった*h。一方、TSのドパミン活動性はNAcと逆のパターンを示し、この変化も日数の経過により強化され たが*i、ストレス耐性による個体差は認められなかった*j。行動分析と組み合わせた分析でも、NAcのドパミン活動性は、ストレス耐性群では反撃するときに増強し、逃走するときに減弱したが*k、ストレス感受性群では反撃するときに減弱し、逃走するときに増強した*l。この結果は、ストレス耐性の低い個体ほど、侵略マウスへの接近や攻撃に嫌悪を感じ、その終了に安堵を覚える傾向があることを意味する。
最後に、NAcのドパミン神経を人為的に刺激するとストレス耐性が変化するのかを検討した。マウスのNAcに光ファイバー埋込とオプシン発現を行った上で、社会的敗北ストレスに曝露し、光遺伝学的刺激でドパミンを活性化させた。その結果、ストレス曝露中にランダムに活性化させた場合や*m、反撃するタイミングで即時に活性化させた場合に*n、刺激しない対照群と比較して社交時間が長くなり、ストレス耐性に関連する行動戦略の増加も認められた。この結果から、ストレス曝露時の行動に基づくドパミン活性化が、ストレス感受性の予防に役立つ可能性が示された。
Willmoreらは「ストレス耐性のある個体は、そうでない個体とは異なる行動戦略、ドパミン神経の活動性を持つことが示された。さらに、ストレス曝露時のドパミン活性化により、ストレス耐性に関連する行動パターンを促進できることも判明した」と結論付けている。(編集協力HealthDay)
Copyright © 2023 Lundbeck Japan. All rights reserved.
注釈
*a
t-test for equal means t = 2.66, P = 0.01, Levene test for equal variance W = 5.46, P = 0.02
*b
one-way ANOVA、F(51,2)=3.21、P=0.048
*c
一般化推定方程式(各個体を経時的に繰り返し測定した値との相関の線形モデル)、N=32、Z=2.01、P=0.045
*d
一般化推定方程式、N=32、Z=−2.05、P=0.040
*e
一般化推定方程式、N=32、Z=2.42, P=0.016
*f
one-sided normal test for proportion>0.5、P=3.0×10^-6、N=32
*g
接近開始時の一般化推定方程式、社交時間と日数の相互作用:社交時間のmain effect、Z=1.98、P=0.032、日数のmain effect、Z=−0.93、P=0.35
接近終了時のTwo-sided一般化推定方程式、社交時間と日数の相互作用:社交時間のmain effect、Z=−2.77、P=5.7×10^-3、日数のmain effect、Z=3.84、P=1.2×10^-4
*h
一般化推定方程式、N=27、接近開始時Z=1.98、P=0.032、接近終了時Z=−2.77、P=0.006
*i
接近開始時の一般化推定方程式:日数のmain effect、N=27、Z=4.973、P=6.6×10^-7
*j
Two-sided一般化推定モデル、社交時間と日数の相互作用
接近開始時のストレス耐性のmain effect、Z=−0.24、P=0.81、日数のmain effect、Z=4.973, P=6.6×10^-7
接近終了時のストレス耐性のmain effect、Z=0.388、P=0.70、日数のmain effect、Z=−0.059、P=0.953
*k
Pearsonの相関、N=19、それぞれR=0.49、P=0.035、およびR=−0.8、P=3.7×10-5
*l
Pearsonの相関、N=19、それぞれR=0.47、P=0.041、およびR=−0.56、P=0.013
*m
社交時間:two-sided t-test、N=14対N=14、t=2.19、P=0.037、それに伴う行動戦略の増加:N=14、Two-sided correlation、R=0.74、P=0.0026
*n
社交時間:two-sided t-test、N=16対N=14、t=2.29、P=0.030、経時的な行動戦略の変化:Paired t-tests、two-way FDR corrected、タイミング刺激群でt=2.77、P=0.029、対照群でt=−0.41、P=0.69.