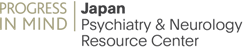精神薬理学分野の研究と臨床実践:エキスパート編(前編)臨床現場の「なぜ?」が、精神薬理研究の道を拓く 精神医学クローズアップVol.25
精神科医療において、薬物療法は治療の根幹を支える重要な要素の一つです。
そこで日本の薬理学研究を牽引し、豊富な臨床経験を持つ稲田健先生をファシリテーターにお迎えし、「精神薬理研究と臨床実践」をテーマにしたシリーズ記事を企画しました。
第1弾は、精神薬理学のエキスパートの1人である古郡規雄先生との対談です。
本対談の前編では、精神薬理研究との出会いから、目の前の患者さんに直接役立てたいという思いが、研究の道へといざなった経緯について語っていただきました。また、研究継続の原動力、臨床医としての視点、そして若手医師が研究を成功させるためのヒントについて、両先生の経験に基づいた視点でお話しいただきました。
稲田 健 先生
(北里大学医学部 精神科学 主任教授)<ファシリテーター>
古郡 規雄 先生
(獨協医科大学 精神神経医学講座 主任教授)
「目の前の患者さんに直接適用できるような研究をしたいという思いが、臨床精神薬理の道へ」(稲田先生)
精神薬理研究との出会いとあゆみ
稲田 はじめに、自己紹介も兼ねて、精神薬理分野に進まれたきっかけから伺いたいと思います。私の場合は最初から精神薬理をやろうと思っていたわけではなく、大学院時代に脳科学に興味を持って生理学の研究室に所属し、そこでグルタミン酸受容体に関する基礎研究に携わる機会を得たのが始まりです。実験を重ねていくうちに、脳の中で起きていることを少しずつ想像できるようになり、薬の研究への興味が増していきました。その後、「目の前の患者さんに直接適用できるような研究をしたい」という思いが強くなったこともあり、次第に基礎研究から臨床精神薬理の領域へと関心が移っていきました。学会や研究会に通っているうちにだんだん知り合いが増え、刺激を受けて臨床精神薬理研究が楽しくなり、今に至っています。
古郡 私が医学部を卒業した頃は臨床初期研修制度がなく、直接精神科に入局すると同時に大学院に入学するという「ダイレクト入局」の時代でした。薬理にもともと興味があったわけではありませんでしたが、大学院で研究グループを決める際に、日々の診療に直結する研究であると思い、薬理グループを選びました。当時のグループを率いていた大谷浩一先生(元・山形大学医学部精神医学講座 教授)が「研究も臨床も、どちらもおろそかにしてはならない」という姿勢でしたので、17時までは臨床に立ち、その後の時間で研究を行うという生活をしていました。当時は薬物動態学がテーマでしたが、薬剤を研究すると同時に臨床での薬物療法を相当意識していました。
「今まで研究を続けられたのは、臨床において、研究で得られた知識を基に治療を行っているという自負があるからです」(古郡先生)
稲田 入局後に研究を始めて、今まで研究を続けられたのはどのような理由からでしょうか。
古郡 入局して半年後に、薬物代謝の世界的な研究者であった石崎高志先生(元・国立国際医療センター研究所 臨床薬理部長)の研究室に短期留学をし、そこで刺激を受けたことが大きいです。2年目に外の病院での勤務を始めて、患者さんのサンプリングができるようになると、自ら臨床評価を行い、血液サンプルを採取してデータをまとめる作業は非常に興味深いものでした。
これまで研究を続けてこられた理由は、通常の精神科医では持ち得ない知識を基に薬物治療を行っているという自負があったからです。私の医師としての原点は、病気を解明したいというよりも、「患者さんを良くしたい」という思いにあります。現在も、自分の中では研究者よりも臨床医としての比重が大きく、より良い臨床を実践するために研究するというスタンスで仕事をしています。
稲田 古郡先生も私も、主なフィールドは日本臨床精神神経薬理学会になるかと思います。2024年より本学会の理事長に就任されましたが、以前と比べてどのように変わってきているとお考えですか。
古郡 以前は自施設でコツコツと投薬データを集めるなどの小さな研究が主流であったと思いますが、現在ではそのような小規模な研究は通用しなくなってきています。共同研究という形で、みんなでデータを持ち寄るという形にシフトしているのではないでしょうか。特に、国際誌への掲載を目指すのであれば、共同研究という手法が必要になってきていると感じています。
「将来的には必ず患者さんに役立つという、ストーリーを持った研究をしてほしい」(古郡先生)
学会の場で仲間を作り、大きな研究へ
稲田 私が精神薬理研究を続けてこられた理由の一つに、「仲間がいるから」というものがあります。毎年同じ学会に参加していると、同じような興味を持っている先生方が集まってきてお互いに議論を行う。すると来年も参加したいというモチベーションにつながっていったと感じています。このように学会や研究会で仲間を作るという意味合いについて、どのようにお考えになりますか。
古郡 私は学会では、仲間を作ることと後進を育てることが大きなテーマになるのではないかと考えています。自分の研究成果を発表することや他の研究を聞いて刺激を受けるというのが本来の学会のあり方かもしれませんが、同じ価値観を持っている先生方と一緒になって、より大きなテーマで仕事をしようという場になっていると思いますね。
あとは若手を鍛える場でもあると考えています。日本の臨床精神薬理学を発展させるためには、核となる人たちに牽引してもらう必要があります。ですので、有力な候補の人たちに研究のあり方や進め方について議論をする場を設けていました。
稲田 「薬理塾」や学会「前夜祭」なども自発的に行われていましたね。塾長からのオーダーとして「明日からの学会で必ず1個は質問すること」いうのが非常に思い出深いのですけれども、それを笑いながらやっているとお互いに刺激をし合えますし、先生がおっしゃるところの“鍛えられる”につながるのだろうと思います。
古郡 質問をするということは、それなりにバックグラウンドの基礎知識が必要なので勉強しますから。また、どうしても「データを出したい」とか、「論文を書きたい」という意識が先行してしまうと研究のための研究となり、臨床的な意味合いが不明瞭な研究となってしまうので、若手の先生方に向けては「きちんと臨床的な意義を意識してやってほしい」という話をしています。
稲田 前夜祭のときに「何を質問していいか分からなかったら『その研究は何の臨床に役に立つのですか』と質問しなさい」という話がありました。自分が今この立場になってみますと、大学院生の学位審査においても、「この研究成果が、明日の患者さんや医学のためにどういう意味を持つのですか」というのは非常に重要な質問だと思いますし、そこに答えられていないものは学位論文として認めにくいと思いますので、大事な視点ですね。
古郡 たとえ動物実験であっても、その研究が将来的には必ず患者さんの役に立つという、ストーリーというか道筋がきちんと見えていればよいと思います。
「日常診療における臨床での疑問が研究への種となる」(稲田先生)
臨床の現場には研究のヒントがあふれている
稲田 精神薬理に限らず、研究は医学の発展に資するだけでなく、臨床医個人のスキルアップにもつながります。二つの側面から患者さんのベネフィットを高めていく重要な活動なので、ぜひ多くの先生方に参加していただきたいのですが、研究に関心はあっても臨床が忙しく、なかなか踏み出せないという先生方もおられると思います。どのようなことから始めていったらよいのでしょうか。
古郡 最初のステップとして、ケースレポートを書いて学会で発表することをお勧めします。次に、そのケースレポートを論文化するのですが、これは意外と大変で、実はこの作業を行うことによって臨床力が高まるので、必ずやってほしいと考えています。その次は、ケースシリーズとして似たような症例を5例、10例と集めていって、何か共通性を見つける。それができるようになったら今度は研究計画を立ててしっかりとしたデータを集めていく、というように段階を踏んでやっていくのが比較的無理のない研究の進め方ではないかと思います。
稲田 学会で賞を取るような研究は研究計画がしっかりしていて、多施設共同研究であったり、基礎研究とのコラボレーションがあったりします。そういった立派な研究をいきなり見せられて、そのやり方を説明されても、なかなか手をつけられないと感じる方も多いかもしれません。
古郡 大規模な研究を見ると、「こんなにエフォートはかけられない」と思ってしまい、手が出せなくなってしまいます。その点、ケースレポートなら自分が経験した症例なので、誰よりもそのケースをよく知っています。ですから、労力的にはそれほど大変ではないはずです。
稲田 北里大学では患者数が多く、バリエーションの幅もかなり広がり、以前と比べて臨床が非常に忙しくなりました。そうすると「臨床でやっているこれは正しいのかな」、「これは常識だと思っていたけれども、本当にそうなのかな」と思うことが増えてきました。ですので、それを一つ一つケースレポートやケースシリーズにまとめ、研究として発展させることを目指しています。
古郡 ぜひ若手の先生方には、メンタルクリニックや精神科病院などで臨床にあたっておられる先生方とコミュニケーションをとることをお勧めします。そうした施設は症例数が圧倒的に多いので、研究データとは違う臨床家の知恵や情報、研究につながるヒントを学ぶことができます。私自身も、相互作用が起こりえないと思っていた薬で中毒が起こり、あとから基礎研究でその機序が明らかになったケース1をはじめ、臨床で理論上ではありえないことに遭遇し、それが研究の発端となったことがいくつかあります。
稲田 研究から追いかけていくのではなく、先に現象があって、研究によってそれを解き明かしていくという流れがあるのですね。
古郡 日常の臨床で、「何だかよく分からないね」と言って終わっているケースは思いのほか多くあるのではないでしょうか。それを丁寧に見ていくと、次の研究のヒントがたくさん隠されているのではないかと思います。
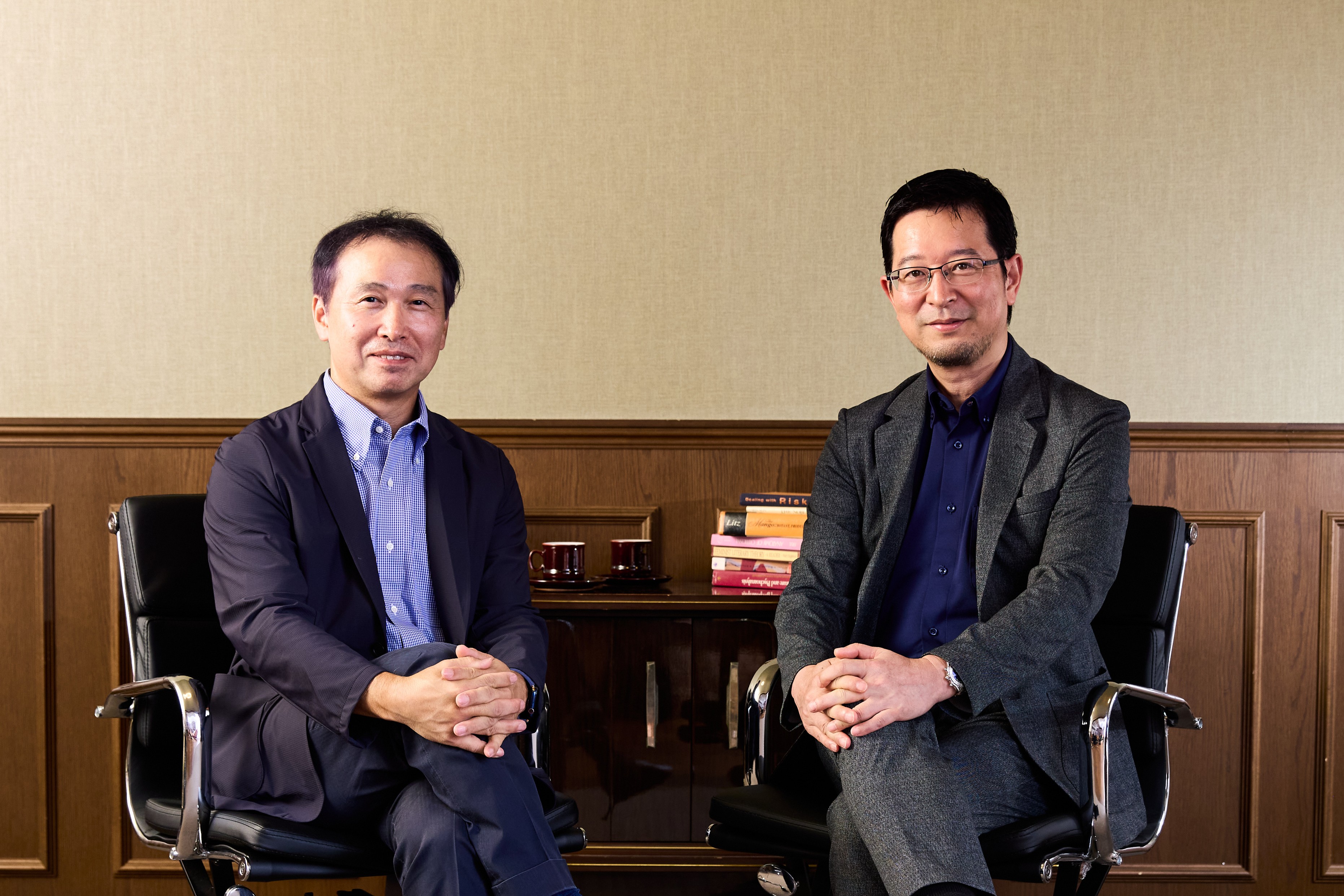
<プロフィール>
稲田 健 先生
北里大学医学部精神科学 主任教授
1997年北里大学医学部卒業。その後、北里大学医学部精神科に入局。米国ノースカロライナ大学留学、東京女子医科大学医学部精神科医学講座助教、同講師、同准教授を経て、2022年より現職。専門分野は精神薬理学、精神科学。日本臨床精神神経薬理学会評議員、日本神経精神薬理学会理事、日本精神神経学会代議員、日本うつ病学会評議員、他多数。
古郡 規雄 先生
獨協医科大学精神神経医学講座 主任教授
1993年弘前大学医学部卒業。その後、弘前大学医学部神経精神医学講座に入局。スウェーデンカロリンスカ研究所臨床薬理学教室留学、獨協医科大学精神神経医学講座准教授を経て、2023年より現職。専門分野は薬物治療、リエゾン精神医学、認知行動療法。日本臨床精神神経薬理学会理事長、日本神経精神薬理学会副理事長、日本うつ病学会評議員、日本統合失調症学会評議員、他多数。
取材/撮影:ルンドベック・ジャパン Progress in Mind Japan RC
取材日:2025年7月27日
取材場所:TG studio 日本橋人形町(東京都中央区)
Progress in Mind Japan Resource Centerは、会員の皆様が安心して自由に意見交換できる場を提供することを目指しています。
本コンテンツに登場する先生方には、Progress in Mind Japan Resource CenterのWebコンテンツ用の取材であることを事前にご承諾いただいたうえで、弊社が事前に用意したテーマに沿ってご意見・ご見解を自由にお話しいただき、可能な限りそのまま掲載しています。
お話の内容は、すべての患者様や医療従事者に当てはまるものではなく、またそれらの内容は弊社の公式見解として保証するものではありません。